近年、世界的に緊張が高まる中で、株式市場でも「防衛関連株」への注目が集まっています。
ウクライナ情勢、台湾問題、そして日本の防衛費増額。これらのニュースをきっかけに、防衛産業に関わる企業の株価は大きく動いてきました。
とはいえ、「もう上がりすぎでは?」「今から買っても遅くない?」と感じている人も多いはず。
この記事では、地政学リスクと防衛関連株の関係をわかりやすく整理しながら、2025年に注目すべき企業と投資戦略を紹介します!
防衛関連株とは?注目が集まる背景
なぜ今「防衛関連株」が話題なのか
防衛関連株とは、国の安全保障や防衛装備に関わる製品・サービスを提供する企業の株式を指します。
近年は、世界各地での軍事的緊張の高まりを背景に、防衛産業への投資が拡大しています。
下図の三菱重工業のチャートを見ても分かる通り、右肩上がりに株価が上昇していることが見て取れます。

特に日本では、2022年に政府が防衛費を5年で約43兆円へ増額する方針を打ち出して以降、関連企業の業績・株価が大きく注目されるようになりました。
この動きは一過性ではなく、「国の安全保障政策」が長期テーマとして続くことが見込まれています。
地政学リスクと株価の関係をわかりやすく解説
地政学リスクとは、国際的な対立や紛争、外交政策の変化などが経済に与える影響を指します。
一般的に、リスクが高まる局面では防衛・エネルギー・インフラ関連株が買われやすい傾向があります。
投資家は「不安定な時期ほど、国の安全を守る企業が強い」と考えるため、防衛関連株は“リスクヘッジ銘柄”として機能する場合もあります。
一方で、平和的な情勢が続くと需要が一時的に落ち着くこともあり、中長期視点での見極めが欠かせません。
どんな企業が「防衛関連株」に分類されるのか
防衛関連企業は、兵器や装備を直接製造するメーカーだけでなく、部品・電子機器・通信・サイバーセキュリティなど、幅広い分野に広がっています。
具体的には以下のような企業が代表的です。
- 三菱重工業(ミサイル・防衛システムの中心企業)
- IHI(航空エンジン・宇宙関連)
- 川崎重工業(艦艇・潜水艦分野)
- NEC・富士通(サイバー防衛・情報通信)
このように、防衛といっても実際には多層的な産業ネットワークで構成されています。
単に“軍需企業”と捉えるのではなく、技術力・研究開発力・政府契約の安定性といった側面からも分析することが重要です。
2025年の地政学リスクと日本市場への影響
ウクライナ・台湾情勢がマーケットに与える影響
ウクライナ戦争は長期化し、台湾周辺では中国と米国の対立が続いています。
この2つの地域リスクは、世界経済の不安要因であると同時に、防衛関連株の「底堅さ」を支える背景にもなっています。
実際、海外ではロッキード・マーチンやノースロップ・グラマンといった防衛大手が堅調に推移。
日本市場でも、これらの動きを受けて国内防衛産業への期待感が高まっているのが現状です。
また、イスラエル問題も相まって、世界平和の不透明さが浮き彫りになっていることも大きな影響を与えています。
日本の防衛費増加と関連企業への追い風
2025年度以降、日本政府はGDP比2%を目指す形で防衛予算を拡充。
この政策は、国内企業の研究開発や装備品生産にとって大きな追い風となっています。
特に恩恵を受けやすいのは、装備品・電子制御・通信インフラを扱う企業群。
政府の長期契約が多く、景気変動に左右されにくい点も投資家にとって魅力です。
アメリカ・ヨーロッパの動きとの比較
米欧では、すでに防衛産業が「国家産業」として成熟しており、株価にも安定した成長が見られます。
一方、日本の防衛関連株は、まだ市場拡大フェーズの初期段階にあり、長期的な伸びしろがあるとも言えます。
「グローバル防衛産業の一角」として日本企業がどこまで存在感を高めるか。
それが今後の株価動向を左右する大きなカギになるでしょう。
注目の防衛関連企業6選【実績+将来性】
① 三菱重工業(7011)― 日本防衛産業の中核

三菱重工は、防衛関連株を語る上で外せない存在です。
防衛装備庁向けのミサイル、防空システム、艦艇など、日本の防衛力を支える主要企業です。
近年は、国産ミサイルや新型迎撃システムなどの開発案件も増加。
また、航空機エンジンや宇宙分野でも高い技術力を持っており、「防衛×宇宙」の両軸で成長が期待されています。
- 政府契約による安定した収益構造
- 為替・素材価格の影響を受けにくい体質
- 宇宙・エネルギー分野とのシナジー拡大
長期的にみると、政策に支えられた“守りの成長株”として位置づけられる企業です。
② IHI(7013)― 航空・宇宙エンジンの技術力

IHIは、航空機やロケットエンジンの開発を行う重工メーカーです。
防衛分野では、航空自衛隊向け戦闘機エンジンの製造や整備を担っています。
特に注目したいのは、エンジン部品・メンテナンス分野の収益安定性です。
防衛だけでなく、民間航空需要の回復も相まって、2025年以降の収益改善が見込まれます。
- エンジン技術の独自性(海外依存度が低い)
- 防衛×民間の両輪でリスク分散
- 次世代エンジン開発への国家支援期待
中長期では、地政学的リスクだけでなく、「技術革新テーマ株」としても注目です。
③ 川崎重工業(7012)― 海洋防衛の主力
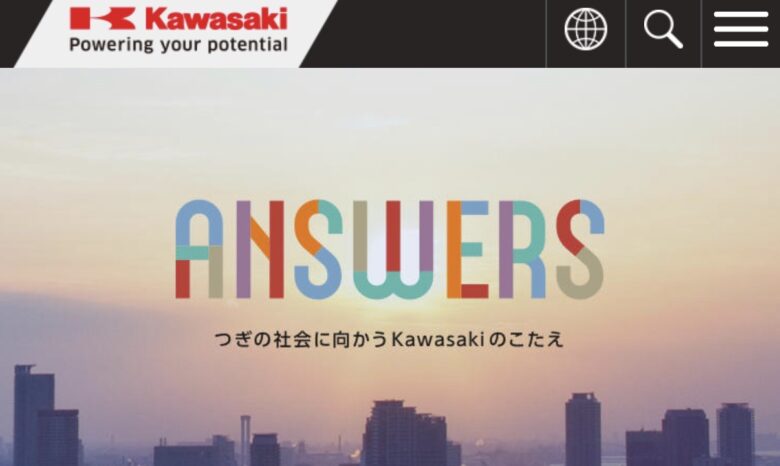
川崎重工は、潜水艦・艦艇・航空機など、海洋防衛を支える技術を有する老舗メーカーです。
特に潜水艦「そうりゅう型」などは海外からも高く評価されています。
防衛事業は全体の売上の約15%を占めており、今後の海上防衛強化方針とともに拡大が見込まれます。
また、水素関連・航空・ロボティクスなど他分野にも積極的で、多角経営による安定性も魅力です。
- 海洋防衛技術の独自性
- 多分野展開による収益安定
- 海外防衛契約の拡大余地
④⑤ NEC(6701)・富士通(6702)― サイバー防衛の要
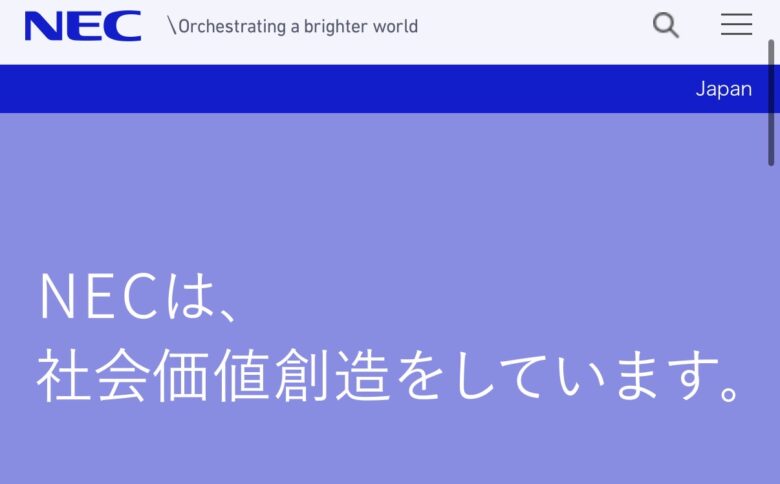
現代の防衛は「物理的な武器」だけではありません。
サイバー攻撃対策、情報通信、防衛ネットワークなど、“見えない防衛”を担う企業の存在も大きいです。
NECと富士通は、防衛装備庁や自衛隊の通信インフラ構築に関わり、国家レベルのサイバーセキュリティ対策を支えています。
今後、防衛費の中でも「デジタル防衛」への比率が高まる見込みです。
- サイバーセキュリティ需要の急拡大
- 官民連携による長期契約モデル
- AI・クラウドとの融合が進行中
これらの企業は、“防衛のデジタルシフト銘柄”として新たな成長フェーズに入っています。
⑥ACSL(6232)

近年では、大手重工メーカーに加え、中小・ベンチャー企業による防衛テック分野も台頭しています。
特にドローンやAI画像解析技術を用いた監視・索敵システムの開発は、注目の成長領域です。
その中でも、国産ドローンの先駆者であるACSLには大注目です!
- 国産ドローンの先駆者
- スタートアップであり、大きなリターンを期待できる
この領域は市場規模がまだ小さいものの、将来的に「日本版防衛スタートアップ」が育つ可能性を秘めています。
防衛関連株に投資する際の注意点とリスク
短期の材料株化に注意
防衛関連株は、ニュースや国際情勢に敏感に反応しやすく、短期的な値動きが激しくなる傾向があります。
「地政学リスクが高まる=株価上昇」とは限らず、過熱感が出た後に急落することも。
投資する際は、「材料が出た直後」ではなく、業績や契約ベースでの成長を確認してからエントリーするのが安全です。
政策依存リスクと為替の影響
防衛関連は国策産業であるため、政府予算や政策変更の影響が大きいのが特徴。
政権交代や方針転換により、受注や利益が変動する可能性もあります。
また、多くの企業は海外製部品やドル建て契約を持つため、為替変動(円高/円安)にも注意が必要です。
今後の展望と投資戦略
防衛関連株は長期テーマとしてどう位置づけるべきか
防衛産業は一時的なトレンドではなく、長期的に国家政策に支えられる分野です。
2025年以降も防衛費増額は続く見通しで、関連企業の受注・設備投資も拡大が予想されます。
短期トレードよりも、「テーマ株として数年単位で保有する」スタンスが有効です。
地政学リスクが落ち着いた時の株価挙動
緊張が和らぐと一時的に株価が調整することもありますが、それは押し目買いのチャンスになりやすい局面。
防衛装備は長期契約・定期整備が中心のため、業績は比較的安定しています。
ポートフォリオにどう組み込むか
防衛関連株は、ポートフォリオ全体の5〜10%程度を目安に組み込むのがおすすめです。
リスクヘッジの意味合いも持たせつつ、景気変動に左右されにくい「ディフェンシブセクター」として機能します。
まとめ:防衛関連株は“買い”か?
地政学リスクが続く2025年、防衛関連株は再び注目を集めるテーマです。
短期的な値動きには注意が必要ですが、長期目線で見れば国策に支えられた安定成長が期待できます。
- 国の防衛予算拡大が継続
- 技術革新(AI・サイバー・ドローン)の追い風
- ESG・倫理面の議論が進み、投資対象として再評価
将来にわたって「平和を守る技術産業」としての位置づけが強まるほど、
防衛関連株は持続可能なテーマ株として存在感を増していくでしょう。
